こんにちは。
星空を見上げると、遠くの銀河や星の光が、はるか昔の情報を私たちに伝えてくれているように感じませんか?
そんな宇宙の謎を解く手がかりとして、人類は電磁波だけでなく「ニュートリノ」という粒子にも注目してきました。
そして今、その観測精度を飛躍的に高めようと、巨大な次世代観測装置「ハイパーカミオカンデ」の設置計画が進行中です。
地下深くに設置されるこの装置が、宇宙や物質の成り立ちを探る鍵となる可能性があります。
ここでは、ハイパーカミオカンデの最新状況を中心に、光検出技術の進展や、以前の開発計画との関係を交えてご紹介します。
巨大地下空洞とハイパーカミオカンデ設置計画

2025年9月、岐阜県飛騨市の山中に、直径69m・高さ94mという巨大な地下円柱空洞が完成しました。
参照:巨大な地下空洞が完成 宇宙と物質の謎に迫る素粒子観測装置「ハイパーカミオカンデ」設置へ(2025年9月25日時点)
地下600mの岩盤中に掘られたこの空間は、次世代素粒子観測装置「ハイパーカミオカンデ」を据え付けるためのものです。
この装置は、旧来のカミオカンデ、スーパーカミオカンデの後継機として、宇宙・物質の本質を探るための重要な施設。
観測開始は2028年を目指しており、設置後には26万トンの超純水を満たすタンクと、2万個を超える高感度光センサー(光電子増倍管)が壁面に設置される計画です。
この規模で観測可能な体積は、スーパーカミオカンデの約8倍。
チェレンコフ光と呼ばれるごく微弱な光を捉えることで、超新星爆発のニュートリノや、理論的に予言されながら未確認の「陽子崩壊」の観測が可能になるかもしれません。
しかし、このような巨大装置を支えるには、空洞構造や耐久性、遮蔽対策、観測精度確保など、技術的なハードルも数多くあります。
そのため、完成に至るまでには慎重な設計と段階的な試行が不可欠です。
ここで補足しておきたいのが、かつて日本で進められていた光検出器関連の研究です。
2020年頃には、ハイパーカミオカンデに組み込まれる光検出技術を見据えた大規模増倍管の開発が進んでいたという記録があります。
これは主役ではないものの、現在の装置設計につながる技術基盤の一部となっていると言えるでしょう。
感度を支える光検出技術─光電子増倍管の性能と役割
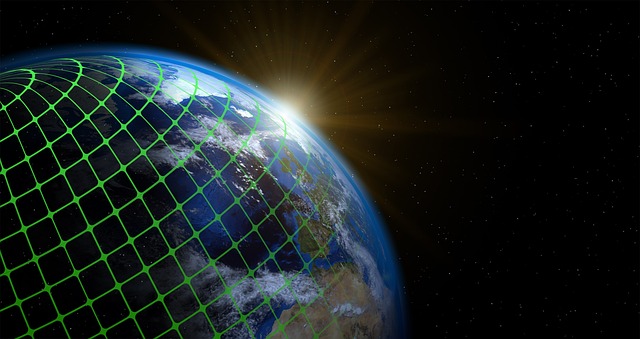
ハイパーカミオカンデの観測精度を左右するのが、光電子増倍管というセンサー群の性能です。
参照:光検出器が新たな物理を探求する─ハイパーカミオカンデが迫る森羅万象と光技術(2020年12月11日時点)
この装置では、チェレンコフ光というごく微弱な光を捉えなければなりません。
ニュートリノが水と衝突した際に発生するこの光は、非常に弱く、取り逃すと観測データになりません。
そのため、壁面に設置される2万本以上の光電子増倍管には、高い検出効率と均一性、時間分解能が求められます。
今回計画されている増倍管は、直径50cm程度の大型モデルが中心とされています。
従来比で検出効率・収集効率・耐圧性などが向上する設計になっており、全てのセンサーが均質に機能するような最適化がなされているとのことです。
さらに、観測においては背景雑音の除去が重要で、外側には別タイプの小型センサーを配置して、宇宙線ミューオンとの区別や雑音の抑制を図る構成も計画されています。
このような補助的な役割があることで、主センサーが本来観測したい光を見逃すリスクを減らす意図です。
この光検出器技術の精度こそが、ハイパーカミオカンデが描くビジョンの実現性を支える根幹と言えるでしょう。
ハイパーカミオカンデは、巨大空洞という壮大な構造だけでなく、光を捉える技術という細やかな工夫との両輪によって成立するプロジェクトです。
2028年の観測開始に向けて、空洞設計、構造耐性、遮蔽・雑音対策、センサー技術といった多層的な開発が並行して進められています。
もしこれらが成功すれば、ニュートリノという存在を通じて、宇宙や物質の深い部分を直接観測できる可能性が広がります。
また、過去の研究や試作機で培われてきた技術は、そのまま現在の装置構成の礎ともなっています。
小さな光を捉えるセンサーと巨大な地下施設が協力し合う姿は、現代科学の挑戦の縮図かもしれませんね。
